「BOX」
(絵:小川咲紀子)
<第一部>
<第二部>
騒がしい。僕は何をしていたんだっけ。ぼーっと目を開くと、無数の雫が空から落ちているのが分かった。雨だ。青々と茂る葉が、僕を守ってくれている。
そうだ、僕は探しものをしていたのだ。しかし何を探していたのか思い出せない。仕方が無いので、手に持っていた傘をさして、とにかく道がある限り、歩き続けてみることにした。
「すみません」
すらりと背の高い女性に声をかけられた。雨に困っているとのことで、傘の中に入ってもらい、共に歩くことにした。
長く続く雨だった。歩くにはなんとも憂鬱で、日差しが恋しくてたまらない。それに雨が降る限り、彼女はここから離れられない。どこか行きたいところがあるのだろうに。
しかし、彼女は嫌な顔ひとつせず、ひたすら僕についてきた。それに彼女との道中はとても楽しかった。意気揚々とジャンプするカエルの姿を見つけてくれたり、濡れた土の匂いを教えてくれた。
僕は”雨が止まなければいいのに”と、思い始めていた。
そんな矢先、雨はあがってしまった。久しぶりの陽の光はなんとも心地のいいものだったが、どこか寂しい気持ちに襲われる。もう、僕が傘をさす必要はなくなってしまったのだから。しかし立ち止まると、彼女は笑いかけた。
「今度は、私が傘をもつわ。あなたと一緒にいることが、とても楽しいの」
僕は彼女の手をとって歩き始めた。
暑い日が続くようになった。道はどこまでも続いているけれど、それはむしろ幸いなことだった。彼女と見たいものがたくさんある。話したいことがたくさんある。全てが新鮮に思えたのは、もう二度と、この瞬間は訪れないと思うようになったからだろう。
だんだんと昼間が長くなっていくことも嬉しかった。反対に、夜の楽しみも増えた。短い夜にいくつ星を数えられるか彼女と競争した。そのうちに眠ってしまうことがほとんどだったけれど。
次第に葉が色づき始め、また季節が変わろうとしているのを感じていた。紅葉を見ながら休んでいると、立派なひげをたくわえた老紳士に話しかけられた。
「私も探しものをしているんですが」
その言葉を聞いて、僕は探しものをしていたことを思い出した。彼女との日々に夢中で、すっかり目的を忘れてしまっていたのだ。
「それでは一緒に歩きましょう」
彼女が老紳士を迎えた。僕は再び探しものについて考えていたが、なんだかもう見つけたような気さえしていた。
だんだんと、夕暮れが早まっていた。冷たい風に、三人で体を寄せ合いながら歩いた。おかげで気持ちはあたたかかった。知識の豊富な彼の話は面白かったし、とりわけ彼に聞いた”こども”の話はとても印象的だった。新しく命が産まれるということ、その命がまた命を産むということ。そんな瞬間に、出会ったことが無かった。
雪も初めて見るものだったが、生まれては溶けてを繰り返すそれは、僕にとってとても不思議なものに思えた。消えていくもの。単純に、そんなものが存在するのだと知った。
雪が溶けてつぼみが膨らみ始めた頃、老人がふと立ち止まった。
「先に行ってくれないか」
「探しものが見つかったのですか」
彼女が寂しそうに訊ねた。
「そんなものかな。見つかったようにも、もうずっと見つからないようにも思える。考えるというのは、とても面倒だ」
大きな木の下に腰掛けて、老人は目を閉じた。
「ただ、君たちと話せて良かった。君たちと過ごしたこの時間で、ひとつ気付いたことがある。それは、君たちとの別れがこんなにも寂しいということだ」
また会えますよ、と言った僕の言葉が彼に届いたのかはわからない。
僕はなかなか、もう彼には会えないという事実を受け入れられなかった。彼女が花冠を持って来てくれても、見向きもできない。ただ、探しものを見つけたいだけなのに、なぜこんな気持ちにならねばいけないのか。寂しくて、悲しくて、もっと一緒にやりたいことがあった。けれど、彼に出会ったことを後悔なんてしていない。彼に出会えて良かったと思う。
彼の最後の言葉を思い出すと、彼の探しものと僕の探しものは、似ているのではないかと感じられた。
そう思い始めた頃には、大きな木はたくさんの花をつけていた。それは今まで見た中で一番美しい花だった。
その木の下に、赤い列車が停まった。
僕は自分で歩くことが怖くなっていた。ただただ、終わりに向かっているように思えたからだ。僕と彼女はその列車に乗ってみることにした。
列車は歩くよりも何倍も速く進んだ。僕は止まろうとしているのに、皮肉にも列車は構わず進んでいく。その間にも何度も朝が来て、夜が来て、季節が巡っていった。
「今あなたは、何が欲しい?」
彼女が訊いた。僕は答えられなかった。
ただ、自分が何を探していたのかをようやく理解した。失うまで、気付けないとは。
赤い列車は、着々と終わりに近づいている。けれど、探しものを理解した僕はもう、それにおびえることはなかった。
朝が来て、夜が来ることの美しさを知った。四季が移り行くすばらしさを感じた。共に箱に入った仲間が、死んでいった。それでも、僕らには新しい命が産まれた。時は、流れる。
また、雨の季節だった。次は僕の終着駅。僕もずいぶん年老いた。新しい命にまた、新しい命が産まれた。僕がこの世界で望んだものは終着駅で失われるけれど、あの世界で望んだものは存分に得ることができた。
「もうすぐ、お別れなの?」
こどものこどもが僕にたずねる。家族を見渡す。
「大切な人を大切だと思うのは、なぜだろうか。
壊れるから、僕らはうつくしいんだ」
駅に着いた時に、彼女が泣きながら
「もう少しだけ、この子たちといます」
そう言って、僕に小さな箱を手渡した。それを持って、僕は赤い列車を降りてゆっくりと歩き出した。
<第三部>
ヒツジは、寝転んでいた。どれくらいこうしていたのかわからないが、とても満ち足りた気持ちだった。
長く、永く、生きるが故に忘れていた命のきらめき。そんな全てをヒツジは思い出した。
彼女に会えるのはもう少し先になるだろう。
手に持っていた小箱を開けると、懐かしい雨のにおいがした。
闇の谷に、美しい朝焼けが広がり始める。
完
2014年3月13日開催
三鷹市公会堂 光のホール
nameshop Oneman Show「BOX」のために
書き下ろした小説です。
<当時のライブの模様>



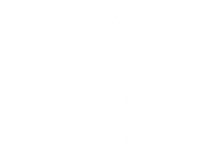


 Online Shop
Online Shop




COMMENT